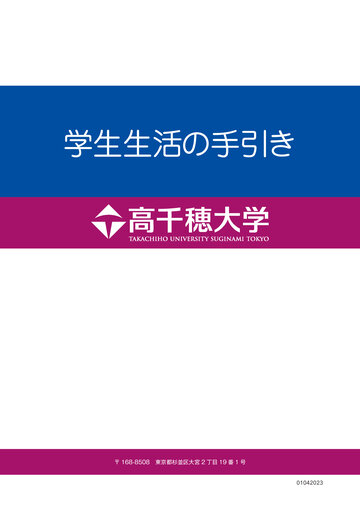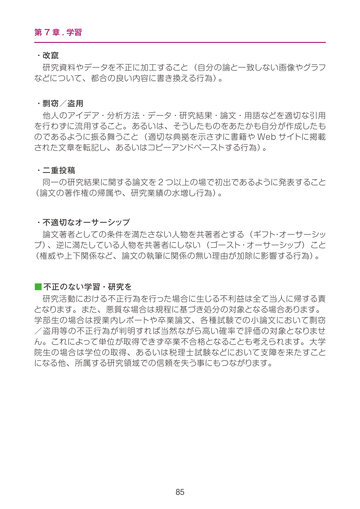高千穂大学 学生生活の手引き
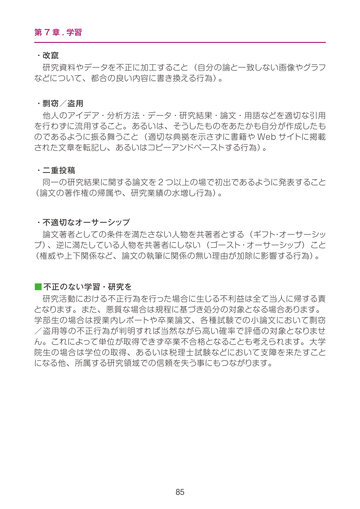
- ページ: 85
- 第 7 章 . 学習
・改竄
研究資料やデータを不正に加工すること (自分の論と一致しない画像やグラフ
などについて、 都合の良い内容に書き換える行為)。
・剽窃/盗用
他人のアイデア・分析方法・データ・研究結果・論文・用語などを適切な引用
を行わずに流用すること。 あるいは、 そうしたものをあたかも自分が作成したも
のであるように振る舞うこと (適切な典拠を示さずに書籍や Web サイトに掲載
された文章を転記し、 あるいはコピーアンドペーストする行為)。
・二重投稿
同一の研究結果に関する論文を 2 つ以上の場で初出であるように発表すること
(論文の著作権の帰属や、 研究業績の水増し行為)。
・不適切なオーサーシップ
論文著者としての条件を満たさない人物を共著者とする(ギフト・オーサーシッ
プ)、 逆に満たしている人物を共著者にしない (ゴースト・オーサーシップ) こと
(権威や上下関係など、 論文の執筆に関係の無い理由が加除に影響する行為)。
■ 不正のない学習・研究を
研究活動における不正行為を行った場合に生じる不利益は全て当人に帰する責
となります。 また、 悪質な場合は規程に基づき処分の対象となる場合あります。
学部生の場合は授業内レポートや卒業論文、 各種試験での小論文において剽窃
/盗用等の不正行為が判明すれば当然ながら高い確率で評価の対象となりませ
ん。 これによって単位が取得できず卒業不合格となることも考えられます。 大学
院生の場合は学位の取得、 あるいは税理士試験などにおいて支障を来たすこと
になる他、 所属する研究領域での信頼を失う事にもつながります。
85
�
- ▲TOP